介護の職場は人間同士の付き合いです。心が通い合っています。しかし、家族でもなければ友達でもありません。
利用者とのやり取りの中で会話は非常に重要な位置を占めています。何をするにも声掛けや同意が必要です。数ある会話の中で、初めは必ずと言って良い程、名前を呼ぶことになります。1日に何回も名前を呼びますよね。
だから、関係はとても深いものになり他人ですが他人ではないような存在になります。
名前の呼び方1つとっても色々なバリエーションがあります。アットホームな介護施設ではニックネームや親しみやすい〇〇ちゃん、そういう呼び方は禁止にして〇〇様、〇〇さんなどあくまでもお客様として意識するという理念がある介護施設もあります。
〇〇さん、〇〇ちゃんなど呼び方は違いますがどちらが良いとは言い切れません。呼称は関係性を構築する上で重要な役割を担っています。
最初に言っておきますが、どちらが良いとか悪いとかそういう話しではありません。呼称で与える影響や効果などを考察していきます。賛否両論あるかとは思いますが、私の考えを書いていきたいと思います。
呼び方がもたらす印象と関係性

呼び方は単なる言葉以上に、関係性や尊重の姿勢を表すもの。
一般的に、〇〇さんや〇〇様という呼び方は少し他人行儀な感じがします。しかし、利用者はあくまでも他人であり、お客様です。ある程度の敬意を示さなければと思います。年配の方なら尚更です。高齢者は長い人生を歩んできた一人の人間。呼び方にはその人生への敬意が込められるべきです。
逆にニックネームや〇〇ちゃんという呼び方も悪くはないですが、良い関係を保つ武器にもなると考えます。より近い関係性にもなりえると思います。
どちらにしろ本人が望まない呼び方は、たとえ親しみを込めたものであっても“尊厳の侵害”になり得ます。
「○○さん」「○○ちゃん」「ニックネーム」など、現場で使われる呼称のバリエーション。
「○○さん」
もっとも一般的な呼び方です。施設によっては、さん付けで呼ばなければいけない所もあるそうです。世間一般では、年配の方など目上の人に使う印象があります。
「○○ちゃん」
親しみやすい呼び方ですね。施設の理念として、アットホームな施設、家族同様に接していきたい、などの考えがある施設には、こういう呼び方は”あり”としているところもあります。しかし、子供扱いされている、馴れ馴れしくしていると思われる事もあるでしょう。
「ニックネーム」
ニックネームは、昔からの友人や家族が使っていることが多いように感じます。その人の生い立ちや昔からの呼び方をニックネームにしている方もいます。本人が好んでいれば良いですが、元々気に入っていない場合もあるでしょう。他の利用者が良く思っていない場合もあるので注意が必要です。
なぜこのテーマが重要なのか?—利用者の尊厳、職員の意識、施設の文化。
その人1人1人に今まで培ってきた人生があります。名前は人生そのもの。呼び方1つでその人の人生を否定してしまうかも知れません。「今までそんな呼び方をされたことがない」「馬鹿にしているのか」そう思う方も少なくないと思います。
職員の働く意識にも影響すると考えます。さん付けで呼ぶと他人行儀だけれど尊厳をもって接してくれていると感じる利用者もいるし、ちゃん付けだと親しみやすく、何でも言える関係にもなり得ると感じます。職員の働くスタンスで1人1人の考えが違います。
呼び方は施設の雰囲気を作る要素でもあります。その施設の理念や方針を写す鏡です。どのような姿勢で利用者と接するのか、「尊厳や敬意をもって接する」「親しみやすく家庭的な感覚で接する」色々な考えがあります。もちろん、介護施設は利用者主体でなければいけません。本人の意見を尊重しながら呼び方を検討しましょう。
「ちゃん付け」は親しみ?それとも幼児化?

利用者に対して「○○ちゃん」と呼ぶ背景:親しみ、長年の習慣、地域性など。
ちゃん付けは親しみを込めるのには効果的だと考えます。利用者も親しみがわけば緊張がほぐれたり、親近感がわき安心出来る環境を得ることができます。利用者にとっては施設は第二の住処として捉え家族のように接していただくことができます。
少なからず地域性も影響しているのではないでしょうか。地方の施設では地域密着型が多く、地元の利用者が多いです。逆に都市部の施設は色々な場所から利用者が集まり、ちゃん付けには抵抗があるように思えます。
利用者の反応はさまざま:「嬉しい」「子ども扱いされているようで嫌」など。
ちゃん付けに対する利用者の反応は様々です。親近感がわいて嬉しく思う人もいますし、高齢者などは子供扱いされていると思う人もいるかもしれません。
言う職員によっても、利用者の反応は違います。利用者自身より年上の職員にちゃん付けされるのは良しとしても年下の職員に対しては抵抗があるということもあります。
利用者の年齢よっても反応は変わってきます。高齢者の方は「子供扱いされて嫌だ」と思う方もいます。障害者施設などは、20代程の低年齢層の方も多くいます。その方々は逆に友達みたいで親近感がわいて嬉しいと思う場合もあります。
施設の利用当初はちゃん付けが嫌だったけど、ある程度利用年数を重ねると職員との関係性も増していき、ちゃん付けも受け入れる場合もあります。
ちゃん付けに対する利用者の反応は本当に様々で、その人の反応を良く観察しながら接していったら良いと思います。「どう呼ばれたいですか?」と聞いてみるのも良いでしょう。
高齢者の人格や人生歴を尊重する視点からの考察。
高齢者の方々は、生きてきた歴史があります。その人の人生や生き様など背負ってきたものは数限りがありません。だからこそその人1人1人の過去を尊重し、敬意を払う必要があると考えます。
呼び方に関しては”さん”でも”ちゃん”でも構わないと思います。しかし、個人を尊重するのであれば、しっかりと利用者本人に聞き取りをし納得していただく必要があるのです。
その人の生い立ちは分かりかねます。アセスメントシートがあればある程度わかる場合がありますが、完全には分からないでしょう。その人を知るにはある程度の年月をかけて接するしかないと思います。介護という仕事は身体的な介助だけではありません。気持ちを汲み取る、察する、そして心をケアするのも仕事なのです。
呼び方を決めるときのポイントと配慮

本人の希望を聞く:呼ばれたい名前、避けたい呼び方。
利用者本人には年齢問わず、こう呼んで欲しいという願望がある方もいます。〇〇さん、〇〇ちゃん、名字で呼んで欲しい、下の名前で呼んで欲しいなど様々です。「名前くらいで・・・」と思われる方もいるとは思いますが、名前はその人の歴史です。過去の生い立ちなど個人的な理由で呼ばれたくない言い方があるかも知れません。名前は、日に何度も口にします。何度も嫌な呼び方をされると嫌になりますよね。相手を傷つけてしまうこともあります。信頼関係も崩れていきます。だから本人に聞く必要があるのです。
家族や過去の呼称との整合性。
家族に聞いてみるのもありかと思います。利用者本人が遠慮して言えない、言いたくない場合もあります。長く暮らしていた家族にしか分からない事も沢山あります。どんな人だったのか、どういう生き方をしていたのか、過去の職業など、聞いてみるのも良いかもしれません。
職員間で統一するか、個別対応するか—施設の方針と現場の柔軟性。
職員によって呼び方が違うと言う事は多々あります。場合によっては現場に混乱を招く場合もあります。職員間の申し送りなどで誰のことを言っているのか判断出来ない場合も無きにしも非ずです。同じ名字の人もいますよね。その場合には下の名前で呼ぶことも職員の混乱防止には役に立つかも知れません。もちろん本人が良ければの話しですが。特に新人のスタッフや非常勤のスタッフなどには混乱を招かないよう注意が必要です。
まとめ

じゃあ何が正解なのか?一番良い呼び方は、本人が望む呼び方です。本人に聞き取りをし呼び方を検討していきましょう。年月が経つにつれ職員と利用者の関係も少なからず変わっていきます。何年、何十年と一緒にいると、まさに家族のような感覚にもなります。若い方が年をとっていき、呼び方が徐々に変化していくこともあります。
名前一つとってみても、奥が深いです。名前はその人1人1人の人生の歴史です。大事にしている物です。本人を尊重し良い信頼関係を結びましょう。
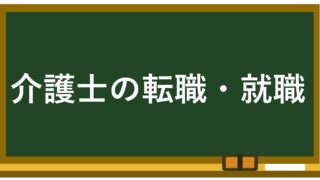
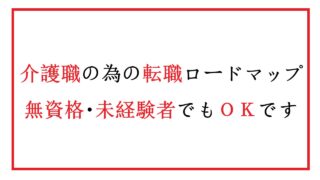
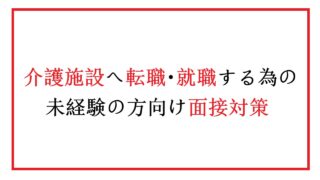
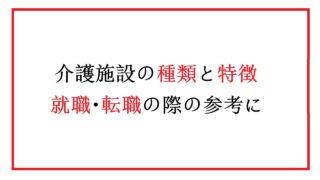


コメント