「入ってみたら思ってたのと違った…」 これは、介護職の転職経験者からよく聞く言葉です。求人票には「アットホームな職場」と書かれていたのに、実際は人間関係がギスギスしていた。研修制度が充実していると聞いていたのに、現場に放り込まれて右も左も分からないまま業務をこなす日々…。そんな“ギャップ”に悩む方は少なくありません。
介護の仕事は、身体的にも精神的にも負担が大きい職種です。だからこそ、働く環境が自分に合っているかどうかは、キャリアの継続だけでなく、心身の健康にも大きく影響します。 施設選びは、単なる「職場探し」ではなく、「自分らしく働ける場所」を見つけるための大切なプロセスなのです。
この記事では、介護職員が転職時に後悔しないために、施設選びで注目すべきポイントを具体的にご紹介します。
※この記事の内容を面接時に確認することは非常に困難です。働いていく中で感じ取れることもしばしばありますのでよく検討を重ね、転職を検討してみましょう。
人間関係と職場の雰囲気

面接時などで施設内を見学させてもらいましょう!施設自体の建物を見学することも大事です。しかし、もっと大事な事は人を見ることです。大事というか・・・それが全てな気がします。人間関係が良好な施設ならば職場の雰囲気も良くストレスがあまりなく働いているので施設内も綺麗ですし整理整頓されています。
挨拶や声かけが自然か
「お願いします」「ありがとうございます」「お疲れさまです」など、基本的なコミュニケーションが交わされているか。無言で業務をこなしている場合は注意!
挨拶が“義務”ではなく“習慣”になっているか
「声かけが“義務的”ではなく“習慣的”に行われているか」という視点は、介護施設の人間関係や職場文化を見極めるうえで非常に重要です。
・職員同士がすれ違うときに「お疲れさまです」「お願いします」といった声かけを自然に交わしているか。
・利用者さんへの挨拶だけでなく、同僚にも敬意を持った言葉を使っているか。
・声のトーンが柔らかく、表情と一致しているか(無表情で機械的な挨拶は逆効果)。
感謝や労いの言葉が聞こえない職場とは?
「ありがとう」「助かりました」「お疲れさまです」といった言葉は、職員同士の協力関係を築くうえで欠かせない潤滑油です。こうした感謝や労いの言葉が自然に交わされる職場では、互いを尊重し合いながら、チームとしての連携がスムーズに保たれます。 しかし、それらの言葉が聞こえない職場では、個人プレーが目立ち、協力体制が弱くなっている可能性があります。職員は「自分の働きが認められていない」と感じやすくなり、次第にモチベーションが低下し、孤立感を抱くようになります。上下関係が顕著に表れている証拠でもあります。結果として、職場全体の雰囲気が冷え込み、ケアの質にも悪影響を及ぼしかねません。 だからこそ、施設見学の際には、職員同士が感謝や労いの言葉を交わしているかどうかに耳を傾けることが、働きやすい職場を見極める大切なポイントとなります。
背景にある「心理的安全性」
習慣的な声かけが根付いている職場では、職員が「ミスをしても責められない」「困ったときに助けを求められる」と感じています。これは「心理的安全性」が高い状態です。
・声かけがある=助け合いができる
・声かけがある=孤立しない
・声かけがある=感謝や労いが伝わる
※心理的安全性が高い職場は、離職率が低く、ケアの質も安定しています。
表情に余裕があるか
眉間にしわを寄せていたり、無表情で動いている職員が多いと、業務過多や人間関係のストレスがある可能性も。笑顔は、職場の雰囲気や職員の精神的余裕を映す鏡です。利用者への笑顔は当然ですが、同僚にも笑顔を向けられる職場は、関係性が良好でストレスが少ない傾向があります。
「目を合わせて笑顔で会話しているか」
・目を合わせることは、相手に対する関心と敬意の表れです。
・笑顔は、安心感・親しみ・協力の意思を伝える非言語的なサインです。
この2つが自然に行われている職場は、職員同士の信頼関係が深く、心理的安全性が高いと考えられます。
※無言で目をそらす職場では、緊張感や不信感が漂っている可能性があります。
「表情がこわばっていないか、眉間にしわが寄っていないか」
職員の精神的・身体的余裕のバロメーター
・表情がこわばっている職員は、緊張・疲労・ストレスを抱えている可能性があります。
・眉間にしわが寄っているのは、集中しているだけでなく、苛立ちや不安のサインでもあります。
・柔らかい表情や穏やかな目元は、職員が安心して働けている証です。
※表情は言葉以上に、職場の“空気”を映し出します。
利用者への影響も大きい
・利用者は職員の表情に敏感です。こわばった顔で接すると、不安や緊張を感じてしまいます。
・笑顔や穏やかな表情は、利用者の安心感・信頼感につながります。
・特に認知症の方は、言葉よりも表情や雰囲気で職員の感情を読み取る傾向があります。
※職員の表情は、ケアの質にも直結します。
こわばった表情や眉間のしわは、職員の余裕のなさや職場の緊張感を示すサインです。 施設見学では、言葉よりも“顔”に注目することで、職場の本質が見えてきます。 笑顔が自然に出る職場は、働く人も、利用者も、安心できる場所です。
忙しい時間帯でも、協力し合う姿勢が見られるか
介護現場は時間に追われることが多く、忙しいときこそ職員の本音や連携力が表れます。介護施設ではチームワークが必須です。協力し合える職場は、業務の負担が分散され、ミスや事故の防止にもつながります。
「自然な声かけがある職場は“助け合い”が根付いている」
・「ちょっと手伝ってもらえますか?」という声が自然に出る職場は、助けを求めることが恥ではないという文化が根付いています。
・「ありがとう、助かった!」という返しがあることで、感謝の気持ちが共有され、信頼関係が深まります。
・こうしたやり取りが日常的に行われている職場は、チームワークが強く、業務の質も安定しています。
※声かけが自然に飛び交う職場は、職員同士が“仲間”として働いている証なのです。
「忙しい場面こそ“声かけ”が職場の質を映す」
・忙しい時間帯(例:朝の起床介助、夕の臥床介助、食事前後、入浴介助など)は、職員同士の連携が不可欠です。
・「○○さんお願いできますか」「そっちは終わりました?」などの声かけがあることで、業務の流れがスムーズになり、ミスや事故のリスクも減少します。
・無言で動いている職場では、連携が不十分で、個人プレーに偏っている可能性があります。個人プレーが蔓延すると事故の原因になりかねません。
※声かけは、チームとして機能しているかどうかの“見える化”です。
「声かけがしやすい=心理的安全性が高い」
忙しいときでも声をかけ合える職場は、「頼ってもいい」「話しかけても迷惑じゃない」という安心感が根付いている証であり、逆に無言で業務をこなしている職場では「話しかけづらい」「空気を読まなきゃ」といった緊張感や遠慮が漂っている可能性があり、こうした声かけのしやすさこそが職場の“心の余裕”を映すバロメーターだと言えます。
教育・研修制度の充実度

新しく入職しました。いきなり現場での仕事をさせられてしまう。しかも殆ど教育はされないまま・・・そんな話しはよく聞きます。介護施設は人員不足な所も多々ありそういう場面に出くわすことも珍しくありません。しっかりした介護施設は、職員を大事にすると同時に利用者も大事にします。教育不足のまま、現場に放り出されるとどうでしょう・・・困るのは職員だけではないですよね。もちろん利用者も困ります。介助を知らない人から介助されるのですから。人によって身体状況は様々です。人によって介助方法を変えなければなりません。教育という事がどれだけ大事なのか、それが分かっていない職場は働く職員も苦痛でなのです。
新人教育の有無と内容
介護施設では入職したらオリエンテーションが必要です。虐待防止・身体拘束・権利擁護等の机上教育が必要なのです。もちろん介護技術は学ぶ必要があります。それを疎かにしている介護施設は良い施設とは言えません。
「入職時のオリエンテーションがあるか」
・入職初日は誰でも不安を感じるもの。そこで施設側が理念や業務内容、感染対策などを丁寧に説明してくれると、「歓迎されている」「大切にされている」と感じられます。
・逆に、説明が不十分だったり「現場で覚えて」と丸投げされると、不安や孤立感が強まり、早期離職につながることも。
※オリエンテーションの質は、職場の“育てる姿勢”を映す鏡です。
「OJT(現場研修)の体制が整っているか」
・OJTとは、実際の業務を通じて先輩職員から指導を受けながら、仕事を覚えていく研修スタイルです。
・介護現場では、マニュアルだけでは分からない「利用者ごとの対応」「チーム内の動き方」「声かけのタイミング」などを、OJTで身につけていきます。
OJTの体制が整っている施設は、職員の成長を支える仕組みがあり、安心して働き始めることができます。 「誰が教えるか」「何を教えるか」「どれくらいの期間か」が明確な職場ほど、教育の質が高く、定着率も安定しています。
※OJTが整っている職場は、職員の成長を“現場全体で支える”意識があります。
「資格取得支援制度の有無」
・実務者研修や介護福祉士取得に向けた費用補助があるか
・勤務扱いで研修に参加できるか(公休・有給での参加)
・外部研修や勉強会への参加を推奨しているか
※資格取得支援制度が整っている施設は、職員の成長を大切にし、長く働いてもらいたいという姿勢が感じられます。 制度の有無だけでなく、費用・時間・学習サポートの“中身”まで確認することで、安心してスキルアップできる職場を選ぶことができます。
業務量と人員配置

業務量が過剰で、人員配置が不十分な施設では、どんなに理念が立派でも、職員が疲弊してしまいます。 「無理なく働けるか」「安心して夜勤に入れるか」「自分の役割に集中できるか」——この視点で施設を見極めることが、長く介護職を続けるための第一歩です。
「業務の分担が明確か」
・業務の分担が上手くいっていないと個人の負担が大きくなり疲弊してしまう。
・介護士の仕事以外に看護・事務の仕事も任されてしまう。
・違う介護業務を任された職員が他部門にも協力的であるか。
※業務の効率化を図る為にも、業務の分担は重要なことです。1人で全てこなすことは無理です。心身共に疲弊してしまいます。
「夜勤体制が安全か(ワンオペか複数か等)」
・夜間も看護師が在中しているか。オンコール体制があるのか。
・仮眠や休憩時間があるのか。
・入所者の数に対し職員の配置人数が適切か。
※夜勤は利用者の急変や転倒リスクが高まる時間帯。ワンオペ(1人体制)だと、緊急時の対応が遅れたり、精神的な負担が大きくなります。
給与・福利厚生・待遇

介護職の給与は「基本給+各種手当」で構成されることが多く、手当の有無や金額によって実質的な収入が大きく変わります。基本給はもちろんのこと、介護職特有の実務者研修・介護福祉士の手当は面接時には、しっかりと聞いておきたいところです。そして、夜勤手当も聞いておきましょう。このような手当は介護施設によって様々です。
「基本給+手当の内訳が明確か」
・基本給が年齢や経験に見合っているか。
・処遇改善手当が適正に支給されているか。
・各種手当てを他施設と比較してみる。
処遇改善手当とは
介護職員の給与を引き上げるために、国が介護施設に支給している補助金のことです。 施設はこの補助金をもとに、介護職員の給料やボーナスに上乗せする形で支給しています。
「有給取得率や残業の実態が説明されているか」
・有給取得率がどれぐらいか。
・希望休は何日取得できるか。どれくらい希望が通るか。
・残業は月に平均何時間あるか。
※実際に取得されている実績があっても、現場の雰囲気や、上司の顔色を伺いながらの取得は気持ちよく休めません。その他にも産休や育休の取得についてもあらかじめ聞いてみましょう。男性の育休も当たり前の時代です。男性の取得実績も聞いてみて下さい。
その他の福利厚生
・交通費の支給はあるのか。
・退職金制度の有無と支給条件。
・住宅手当の有無。
※上記の手当は、各施設にかなりのバラツキがあるように思えます。計算方法や支給条件も合わせて聞いた方が良いですね。
施設の理念と運営方針

理念が「利用者の尊厳を守る」「その人らしい暮らしを支える」といった内容であれば、ケアの質を重視している可能性が高いです。一方で、職員の安全や働きやすさを軽視していると、現場が疲弊しやすくなります。ホームページなどを確認すると施設の敬遠方針や掲げている理念も分かるかと思います。
介護施設のSNSなどの情報発信は今や当たり前の時代です。ホームページやFacebook、インスタグラムを開設している施設は多いです。逆にそれらがない場合は時代に逆行している、そこまでの余裕がない、経営方針が古い可能性が高いです。経営陣の考えが古いと職員に対する考え方も古いです。一昔前は、終身雇用が当たり前な時代です。しかし、今では転職は当たりまえ、転職してスキルアップするのが当たり前の時代です。古い考えの施設に付いていく必要はあまりないように思えます。
まとめ

就職や転職は人生の大きな転機になります。面接時には聞くところはしっかりと聞くことが今後の人生を大きく左右します。実際に私は、面接に携わって色々な人を面接させていただきました。聞き過ぎて気分を害することはありません。むしろしっかりしているなぁと感心いたします。
面接時に施設を見学しても分からない事は沢山あります。実際に働いてみないと分からない事は多々あります。これからの人生、後悔せずに思いの丈をぶつけてみて下さい。そして、自分に見合った介護施設を見つけて下さい。
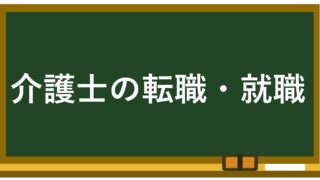
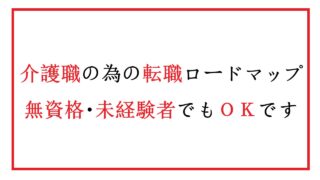
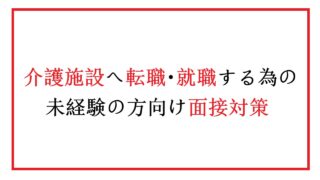
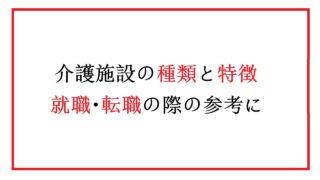



コメント